自信やアイデンティティーは子供の頃に培われる。トミー・ゲレロのクールな生き方から学ぶ(2/2)
-
INTERVIEWS:
トミー・ゲレロ/Tommy Guerrero/Skateboarder/Musician
Fuck You精神とD.I.Y.精神とは、「自分が絶対だと思う価値を譲らず、自分で動く」という心持ち。いま子供達は知識を詰め込む選択肢しか与えられず創造力を養う時間がない。友と自由に遊び、好奇心を育み、挑戦する勇気や責任感を養うことは鳴りを潜めてしまった。だけどいま必要なのは「ゆとり」ではなく「野性」という生まれたままの本能むき出し100%ピュアな荒々しい処方箋。トミー・ゲレロという治療法がここにある。

一日の半分は息子と一緒にいるよ。学校に息子を迎えに行ったり、夕食を作ったり、家に連れて行ったり、朝、彼の弁当を作ったり、学校に連れて行ったり。僕の時間の大部分だよ。
少し前まではKrookedのレイアウトとデザインをやっていたし、ボードのデザインからレイアウト、広告やカタログデのザインまで、スケートボードに関するありとあらゆることをやっていた。だけどあるときに手根管症候群と反復ストレス障害になってしまった時、僕がこの地球上に存在する理由はマーク・ゴンザレスの芸術に色を付けることじゃないことに気がついた。僕がここに存在する別の理由があると思ったんだ。それからは黒子になってKrookedのアートディレクションと全体的な方向性を見るようになった。今僕が会社へ持ってこないといけないクリエイティブ・アイディアはとても自由なんだ。たくさんの自由とたくさんの時間があるのはとてもいい事だ。僕はオフィスに入ることはめったにない。だから会社は、僕がすべきことに自由を与えてくれている。一日の半分は息子と一緒にいるよ。学校に息子を迎えに行ったり、夕食を作ったり、家に連れて行ったり、朝、彼の弁当を作ったり、学校に連れて行ったり。僕の時間の大部分だよ。

大きい企業では、直感を信じて良いことをしようとしても、みんなのことを考慮しないといけないし、その他にも優先順位があるからその直感が失われてしまう。
REAL Skateboardsは、90年か91年の終わりころから始まった。僕とジム・ティボーは同じチームでスケートしていたし、何かスケートに関することを一緒にやりたいといつも言っていた。僕はスケートすることが出来る時間には、いつか終わりが来ることを理解していた。エリック・スウェンソンとファウスト・ヴィッテロの2人がオーナーでIndependent Trucksを始めていて、彼らのことは小さい頃からよく知っていた。彼らがIndependent TrucksやThrasher Magazineを始めるずっと前からね。彼らが僕に言ったのさ「何か面白いこと一緒にやらない?」ってね。DELUXEはすでに存在していてThunder trucksとSpitfire wheelsがあったから、僕たちは一緒にボード会社REALを作った。それでパウエル・ペラルタを離れてREALを始めた。当初は4人だけで一度に数百のボードを作る会社を作ろうとしたんだ。僕たちはディレクション、ヴィジュアル、ボードデザインなど全てにおいてもっとクリエイティブであるべきだと考えていた。僕らはまだプロスケートボーダーでもあったから、半日働いてスケートボードしに行っていたよ。僕たちが参加する前に、ジェフ・クリントがREAL Skateboardsという名前を思いついた。彼はとてもリテラルな人間だったから「これはくだらないおもちゃのスケートボード。対照的にこれは本当のスケートボードだぜ!」ってね。
会社が始まった当時、僕らは4人だけでカット&ペーストしてグラフィックを作ったり、はさみで切ったり、のりで貼ったり、XEROXでコピーしたり(笑聲)。僕はクリエイティブな人間で、ジムは考えるタイプの人間なんだ。だからお互いに異なったアプローチと哲学を持っていた。ジムは会社全体を掌握して別の場所に連れて行くのが仕事だったし、僕は一歩下がって、とにかく外に出ていま外では何が起こっているのか見て、起こっていることの一部となって体験をして「外ではこんなことを見てきたよ。これが今外で起こっている事で、外で見てきたことだよ。」って伝えた。だから世界で起こっている大半のことは何でも知っていたよ。一方ジムはデスクワークや集中力が凄くてとても働き者だった。
色々な意見があるかもしれないけど、一人がよりクリエイティブな場合は、なかなか難しい。全く考え方の違う二人の人間が一緒に同じことをすることは難しいし、上手くいかない時もある。大きい企業では、直感を信じて良いことをしようとしても、みんなのことを考慮しないといけないし、その他にも優先順位があるからその直感が失われてしまう。45人の従業員がいて、4つのチームがあって少なくともプロのライダーが30人いる。そこにREALとSpitfireという2つのトラックカンパニーがあったから、更に150人のプロのライダーがいた。だから考慮することがたくさんあった。様々なタイプの人間とやりとりもするし、様々な意見や考え方をマネージメントしなければならない。僕は「これで大丈夫だよ、OK!OK!」ってみんなを和解させるようなタイプではない直球タイプだ。僕はこんな風に言うよ「お前は、ろくでなしだ。ファックユー!」ってね(笑聲)。良くも悪くもそれだけの事さ。真実を聞くのが嫌いな人もいる、だから水と油が混ざることは出来ない。多くの人をマネジメントすることは本当に難しい。僕はそれをしない。僕はその一部になりたくないから立ち去った。僕はアイデアが好きだし、クリエイティブな人間でいたい。


だけどもうスケートのテクニック的な側面は求められていなかった。だからボードが着地してから足がボードに着地するフリップトリックのようなトリックはひどく見えた。そこに優美さはなかった。
REALを始めた91年頃は、スケート業界にとっては難しい時期だった。個人的なことではなくて、パウエルから来た僕は会社のためにお金を稼げていたし、自分で全ての請求書を支払うこともできた。だけどパウエルを辞めてこの新しい会社を立ち上げると稼ぎは3分の1くらいになっていた。だから難しい判断だったけど、当時スケートボードを取り巻く環境はドラマチックに変化していた。より小さいボード、小さい車輪、より丈夫な服、すべてがより技術的になっていた。それはスケートボード内に内在する流れにかかわらず、スケートシーンは常に動いている。みんながスケートに対してもっとフリースタイル的なアプローチに変化していた。その流れは、スケートボードを劇的に変化させた。それまでは、この場に止まったまま何百という違った方法でボードをフリップさせて、「これはスペシャルだぜ!ユニークだろ!」って批評し合っていただけなんだ。その場で6時間もスケボーをフリップするセルビデオが撮られていたけど、そこに物事の流動性はなかったし人を惹きつける魅力もなかった、何か新しい事が起こりうる瞬間もなくなっていた。まだそれをやっている人もいたけど、ウィール(車輪)はこんなに大きかったし、凄くスローにスケートしてテクニックを競っていた。だけどもうスケートのテクニック的な側面は求められていなかった。だからボードが着地してから足がボードに着地するフリップトリックのようなトリックはひどく見えた。そこに優美さはなかった。僕の場合、知っての通りストリートでスケートをするスタイルだから、スタイルそのものがまったく違っていた。
スケートボードにとって非常に面白い時期でもあった。僕とジムは頻繁にツアーを回って、スケートボードとREALを広めた。僕達はスケートの世界では信用があったし、みんな僕たちがすることを信頼してくれた。プロのスケートボーダーが自分たちのスケート会社を立ち上げること自体とても新しいことだったし、スケートボード会社の顔として、ボードの形やグラフィックを作って、どうやってそれをデモンストレーションするのかということは革命的だった。僕達は素晴らしいチームだったし、若い素晴らしいスケーター連中もたくさん集まってきてくれた。彼らはREALと僕らが何者かを広める集団的なチームだったし、世界で最高のライダーが所属していた。今でもそうさ。

僕はマネジメントサイドの決定はしない。ビジネスサイドにはいない人間なんだ。自分の意見は述べるけど、完全に僕自身をそこから遠ざけた。
僕はマネジメントサイドの決定はしない。ビジネスサイドにはいない人間なんだ。自分の意見は述べるけど、完全に僕自身をそこから遠ざけた。なぜならチームマネージャーは、新しい連中を連れてきて、時にスケーターを解雇しなければならない。僕にはそれは出来ない。とてもタフなことだ。個人的には、これがビジネスの最も難しい部分だと考えている。なぜなら僕はプロのスケートボーダーだったから会社のために仕事をしている人とは全く違っていた。あの時、僕はパウエルから解雇されようとしていたはずさ、だから僕には気持ちが分かる。歳をとって新しい人がやって来るには部屋を作る必要があるし、それは必然で避けられない。物理的に歳をとることは以前に出来ていたことが難しくなり、これ以上進歩する事が難しくなる。5年のキャリアをもっていたとしても長すぎる。今、スケートでプロとしてキャリアを積める時間はとても短い。アマチュアでもほとんどプロ並みで、ほぼ同じレベルさ。それは驚くべきことだ。だから僕はプロのスケートボーダーを解雇しなければならないという立場にあることを考えることが出来ない。くだらないよ。彼らはスケートボードに命を捧げて、会社のためにライディングして、そして会社のために宣伝をしている。彼らは本当に傷つくだろう。スケートボードすることは素晴らしいことなんだ。だから僕がそのポジションに入ることは難しいと思う。

僕の人生は、まるで魔法のような小さな存在であるかのように見えているかもしれない。でもそれは誰もが同じ事なんだ。みんな立ち上がって、仕事にでかけ、支払いをするために何かをする。世話をする家族があり、足止めする現実があり、身体の障害や欲望、恐れや希望がある。
僕たちは決められた社会の領域で生きているからリスクを取ることは怖い。でも僕たちはこの迷路の中で生きていて、その迷路の中に入る道は一つしかない、同時に外へ出る道もたった一つだけだ。その迷路から新しい出口を見つけることは非常に難しい、だから僕は常に何がやりたいのか?夢は何なのか?時間の経過と共にいつも確かめながら生きてきたつもりさ。明日も生きていられる確証なんてどこにもないからね。数日前にあるスケートボーダーが亡くなった。1ヶ月前に彼に会ったばかりだ。彼は世界中のスケートパークを作っていたGrindlineのマーク・ハバードだ。彼はこの地球にもっと多くのスケートパークを作って、多くの楽しみを人に与えるはずだった。彼の死は突然で、予期せずに亡くなってしまった。僕はどうすれば良いかかわからなかった。だから、いつか必ずやらなければならない時が来る、心の奥で燃えているもの、その内なる情熱を外に出すべき時が来るはずさ。それが何なのか分からないけれどトライし続けなければならない。
僕に関して言えば人生を成功や失敗という観点では見ていない。成功するかどうかにかかわらず、常にやるべきことに対して違った方法を模索しながら、一人の人間として一般的な人生を送るための方法を探しているだけなんだ。僕はいつも自分自身の欠点を、成功や賞賛よりも多く生かす傾向がある。過去に得てきたものは、僕の一部だし最高の形ではないかもしれないけど、自分の人生をやりたいように生きてこれたという意味では成功しているのかもしれない。過去にやり遂げることが出来たのは幸運だったと思う。必要に応じて自分の道を作る方法を見つけられているし、ある程度それが出来たと思っている。だけど今の栄光に満足したことは一度もないよ。僕の人生は、まるで魔法のような小さな存在であるかのように見えているかもしれない。でもそれは誰もが同じ事なんだ。みんな立ち上がって、仕事にでかけ、支払いをするために何かをする。世話をする家族があり、足止めする現実があり、身体の障害や欲望、恐れや希望がある。すべては人間的なレベルで結ばれていて、みんな同じ希望と恐怖と夢と思考とアイデアを持っている。僕たちはとても似ている。本当は僕たちを分け隔てるものなんてないんだ。

息子が産まれて病院で出生証明書に署名するとき、レッド・クラウドをミドルネームで書くと、「何これ?本当にこれでいいの?」って言われたよ(笑聲)。
僕のファミリールーツ曾祖母は、サンフランシスコベイエリアのオーロニ族だった。だから僕の中には先住民の血が流れている。僕が20代前半の時、アメリカ先住民について本を読み漁っていた時期があった。先住民の彼らが経験したすべてのことを知ってとても腹が立った。歴史的にとても悲惨だった。そこで一人のチーフ、レッド・クラウドが立ち上がり初めて米軍に勝った。兎に角インスピレーションを受ける物語でカッコよかった。最後まで戦った不屈の男の物語さ。その背後にある物語が信じられないほど凄い。だから僕の最初のタトゥーはレッド・クラウドだし息子のミドルネームでもある。息子が産まれて病院で出生証明書に署名するとき、レッド・クラウドをミドルネームで書くと、「何これ?本当にこれでいいの?」って言われたよ(笑聲)。アメリカ人でさえレッド・クラウドの事を知らない、自国の歴史に目を背けてる。

これは僕が若い頃にやったことで文字通り「Fuck you!お前が言っていることなんて気にしないよ!」他人が好きじゃなくても関係ない。
息子のディエゴは信じられないけどもう14歳だ。スィートでとてもいいキッズだ。彼は今キックボードのトリックやそのすべてに夢中だよ。それが彼のやるべき事だし、何人かのライド仲間もいるみたいだ。とてもクールだ、僕がスケートで育った時を思い出させてくれる。夢中になれる何かがあるだけでなく、何か満足感や達成感、自信やアイデンティティーは子供の頃に培われる事なんだ。自分は何をしたいのか?自分が誰なのか?何人かの子供はそれらを失ってしまう。非常にハードなことだよ。でもキックボードは、ディエゴにアイデンティティを与え、自分が誰なのかを分からせてくれる。僕がスケートボードで育った時も、スケートはなんのカルチャーでもなかったし、クールでも何でもなかった。だから学校でもどこでもいつも打ちのめされていた。スクーターも全く同じだと思う。キックボードのコミュニティはスケートボーダーから多くの悲しみを学んでいるし、そこから多くのキャラクターを構築している。そこに抵抗して「Fuck you!」って言えることは、とても素晴らしいことだと思う。これは僕が若い頃にやったことで文字通り「Fuck you!お前が言っていることなんて気にしないよ!」他人が好きじゃなくても関係ない。自分が誰であって、人生の中で何を成し得ていくのかってことの自信に繋がる。ディエゴは親切だし、本当優しい。もし彼が自信を持つことができれば大丈夫だと思う。

もしスポンサーがいなかったとしても、それでも僕はスケートを持ってハードに滑っていただろうし、世界中のスケーターがそうしている。
初めてスケートボードを見たのは1975年。ボロボロの板にローラースケートのトラックとウィールが付いているだけのやつ。その直後にBlack Nightと呼ばれているスケートボードを手に入れた。それにはクレイ・ウィールが付いていた。僕が9歳のことだよ。スケートカルチャーは、1970年代半ばにドッグタウンで始まった。トニー・アルバ、ステイシー・ペラルタ、ショーゴ・クボ、ジェイ・アダムスそういった人たちを見て追いかけていた。レッド・ドッグとかもね。その頃からのルーツは理解しているけどそれ以前の60年代は、スチールウィールを使ってスケートボードに乗っていたサーファーも多くいたみたいだけど、そのあたりのルーツはあまり詳しくない。
僕はサンフランシスコで育ったから、ロサンゼルスは遠い世界だった。サンフランシスコから車で約7時間かかるし、家には車がないから旅行したこともなかった。だからスケートボード雑誌だけが情報を得る唯一の手段だった。雑誌が僕らを世界へと繋げてくれる唯一の入り口だった。Z-boysは最先端だった。彼らはボウルやヴォートランプの原型となるプール・スケーティングのパイオニアだったし、スケートの変わり目でボードとランプが出来始めたばかりの頃だね。彼らはそのすべてをスタートさせたし、とても過激で決定的だった。サンフランシスコはアメリカのどの都市とも違っていて、態度やその生き方のすべてがパンクだった。僕らはサーファーじゃない、ただサンフランシスコの街で育つスケートキッズだった。スケートボードが頭から離れない感覚。何かに取り組んでいるとか、何かのために働いているようには考えられない。もしスポンサーがいなかったとしても、それでも僕はスケートを持ってハードに滑っていただろうし、世界中のスケーターがそうしている。

僕らが世界中のどこかに現れると3,000人ものファンが熱狂して叫びながらサインを求められる。非現実的な世界ですらあった。だけど、僕は地に足をつけるように心がけた。僕のエゴが頭の中で膨らまないように。
1984年のコンテストを見たステイシー・ペラルタが僕のスケーティング・スタイルをとても気に入ってくれた。兄のトニーと話をして、僕がチームに加わるように尋ねてきてくれたんだ。ものすごくびっくりしたのを覚えてるよ、僕らはボーンズ・ブリゲードのことをドリーム・チームって呼ぶほどだったからね。実際にボーンズ・ブリゲードはドリーム・チームだったから、その一部になれることが信じられなかったほどだよ(笑聲)。ボーンズ・ブリゲードでの経験はアメージングだった。参加できたこと自体が素晴らしいことだし、スケートという大好きなことをやりながら世界中を旅することが出来た最高の仕事だったよ。チームの誰もがスケートボードのトップにいた連中だし、彼らはとびきり最高だった。そのメンバーになれたことは本当に特別だった。
これだけは言える、よく知られた有名なチームに所属して世界各地をまわって一年中デモンストレーションをしなければならない。家にはほとんどいなかったし、毎日がスケートだった。スケートしていた環境はお湯が沸騰するような天気だったし、順応することは大変だった。そんな中、旅しながらスケートすることは肉体的にも精神的にもとてもハードだった。それでも、スケートして旅することがとても楽しかった。最初はほとんどステーションワゴンで旅して、その後バンでそこら中回ったし、電車などでヨーロッパ全土も回ったこともあった。プロスケートボーダーになったとき、すべてが完全に変わったんだ。それが僕の仕事になったのさ。僕らが世界中のどこかに現れると3,000人ものファンが熱狂して叫びながらサインを求められる。非現実的な世界ですらあった。だけど、僕は地に足をつけるように心がけた。僕のエゴが頭の中で膨らまないように。

ステイシーは常にスケート業界で何か出来ることがないかを考えていた。彼はスケートパークが閉鎖した後に、ストリートシーンに何が起こるのか知っていた。
ステイシーはみんなにとって父親のような存在で、僕達を正しい方向へ導いてくれたチーム・マネージャーでもあった。僕たちは彼が70年代に確立したスケートスタイルや僕たちに残してきたことをとてもリスペクトして育ってきた。単純に誰かが入り込んできて、僕らに何をすべきか教えたり、チームマネージャーになる事と同じではなかった。彼は多くの人たちに信頼されていたし、彼のセンスだったらある意味で簡単なことだったかもしれないけど、僕たちは若くてかなりヤンチャだったから大変だったと思うよ(笑聲)。
ステイシーは常にスケート業界で何か出来ることがないかを考えていた。彼はスケートパークが閉鎖した後に、ストリートシーンに何が起こるのか知っていた。だから彼は僕を雇ってチームに入れた。次に来る波へのアクセス方法を知っていたんだ。「君はドアから出てスケートに行くだけだ。君にランプも裏庭も必要ない。君は自身でランプを組み立て、プールを組み立てる。プールを探し出す必要はない。ただスケートに行くだけだ。」そして彼が見ていた事は現実になった。だから僕は彼がストリート・スケート産業を変えることを助けられたと思っている。あの時は、みんながバートスケートに注目していたから彼は逆にストリートスケートを際立たせた。

ある意味で僕はシンプルに育ったのかもしれない。僕は兄と母と一緒に育ったし、母はとても堅実な生き方をしていた。僕は家族と共に成長しながらアイデンティティーが形成されたから、周りの人達がスターダムになるのを見てきたけど、僕にとってはあまり魅力的ではなかったんだ。
若い時のプレッシャーは別物だよ。若い時は、本当の意味で責任を追っていない。年を取った時のプレッシャーとはまったく違う。家族もいないし何も所有していない。考慮すべき点はずっと少なくて責任はそれほどじゃない。リアルな責任はスケートボードだけだ。コンテストにエントリーした時はとてもプレッシャーがかかる。だけど物事がうまく行くようにプレッシャーはかかるものなんだ。自分自身にプレッシャーをかけたり、会社からプレッシャーを感じたり、ステイシーは僕たちに物事が上手くいくようにプレッシャーがかかることを望んでいた。だから、プレッシャーを感じて困難な時は、相対的にうまくいく時でもあるんだ。もし僕が勝たなくても世界が終わるわけでもない。チームマネージャー以外は誰も気にしないよ(笑聲)。
母は僕がスケートをはじめたその日からとても協力的だった。母はサンフランシスコで、女手一つで僕ら2人の息子を育てていたし、トラブルから僕らを守ってくれた。母は僕たちにポジティブなマインドを与えてくれたし、僕たちがやりたいことは何でもサポートすることを約束してくれた。母は僕らがスケートボードを持って、何か夢中になれることがあればトラブルからも逃れられると考えていた。だから母は、いつも100%サポートしてくれた。ある意味で僕はシンプルに育ったのかもしれない。僕は兄と母と一緒に育ったし、母はとても堅実な生き方をしていた。僕は家族と共に成長しながらアイデンティティーが形成されたから、周りの人達がスターダムになるのを見てきたけど、僕にとってはあまり魅力的ではなかったんだ。それに僕は生まれつき恥ずかしがり屋だからね。ロックスターのように振る舞うことは出来なかったよ(笑聲)。

残念なことにほとんどの人は、自分が好きなことを探すことができていない。
だけど人生は一度きりさ。出来る限り子供の頃にやりたかった事をやろうとして、それをやり遂げる方法を何時間もかけて見つけなきゃ駄目だ。残念なことにほとんどの人は、自分が好きなことを探すことができていない。探し当てることは、宗教じゃないけどスピリチュアルで魂に栄養を与えて豊かにするものなんだ。多くの人はそれを見つけることが出来なくて、そのスペースを埋めようとしている。社会の仕組みは皆がその何かを探すこと、知ることを許さないように形成されてしまっている。探求する能力を失ってしまっている、世界にはもっと美しさがあり、創造性があるのに、みんなにはその余裕がない。それが何であるかを把握して手に職をつけたり、育てるのに必要な時間と余裕が与えられていない。僕たちは仕事、仕事、仕事、仕事のためにセットされてしまっている。それが現実さ。
何であれ、本当に愛している事を頑張ってやるんだ。自分自身にとって価値の有ることをやって感じるんだ。人生において大切なことを見つけトライをする。もしそれが出来たなら後はそれを積み上げ続ける事だよ。何をやるにしても、ただ愛している事をできるだけ沢山やれば、時には何かに繋がることもあるし、時にはドアも開けてくれる。僕は人生というものは非常に短いと思うし、物事は目の瞬きの中で起こり終わっていってしまう。だからそれがとても難しいことだと知っているけど、君たちにはやるべき事をやって欲しい。

スケートボードは全ての人を受け入れてくれる。あらゆる人生を歩んできた全ての人々に対してウェルカムなんだ。
古い言葉にもあるだろ?7回転んで、8回起き上がる。スケートボードから学ぶことはたった1つだ。だってスケートボードは75%から95%がコケるからね(笑聲)。起きあがれなければ、敗北を意味する。だから起き上がり続けるだけさ。スケートボーディングを100%的確に表現している。スケートボードそのものが僕の人生だ。スケートボードは、僕が今ここに存在することや、僕がこれまでにやってきたことすべてをやるための能力を与えてくれた。とても感謝している。そしてスケートボードから選ばれた気もする。スケートに関してはそう感じるよ。
僕はスケートボードがスポーツだとは考えていない。スケートは非常に個性的で様々なスタイルやアプローチがあるから正しくジャッジ出来ないと思う、だから必ずしもオリンピックの種目になければならないとは思っていない。可能な方法としては、ダウンヒルでタイムを競ったり同じようにスラロームやハイジャンプだったり。70年代からやっているやり方だよ。それは基本的に他のスポーツと同じ考えから来ていて、まさにオリンピックの基本に基づいている。「どれくらい高くジャンプができますか?」「どこまで飛ぶことができますか?」「どのくらい速く滑ることができますか?」それはスキーに基づいた倒すことなくコーンを通過するスローラムだよ。そういった側面であれば判断できると思う。だけどグラント・テイラーとニーヤ・ヒューストンのどちらが優れているかなんて事は判断が出来ない。二人とも素晴らしいスケーターなんだ。同じ環境でそれらの二つを判断することは出来ない。例えば僕はグラント・テイラーのスケートを見るのが好きだから、もし僕が判断すれば彼に高い点を与えるだろう。それは決して公平じゃない。だからオリンピックで彼らをどうやってジャッジするつもりなのかわからない。オリンピックのトレーニングに国が関与しているという側面もある。オリンピックのために訓練を受けるなんて全くお門違いさ。スケーターはトレーニングなんかしない。僕たちはただスケートをするだけさ。練習することは、スポーツという側面においての存在方法だよ。スケートボードは、ライフスタイルなんだ。僕にとってはもっと武道のようなイメージが近くて、はるかに精神的なんだ。スポーツは通常チームベースで、全体の仕事をするために他人に依存している。でもスケートボードは自分自身に対するものなんだ。
スケートボードは、人生を通じていつでも傍にあって、自信を忍耐強く、強くしてくれる。困難にあってもくじけない勇気や倫理規範もそうだし、多くのことを教えてくれる。スケートボードは全ての人を受け入れてくれる。あらゆる人生を歩んできた全ての人々に対してウェルカムなんだ。(了)
何かを始める時に感じるスパークの様な初期騒動を忘れなければ大切なものを見失わない。トミー・ゲレロの哲学(1/2)☞戻る

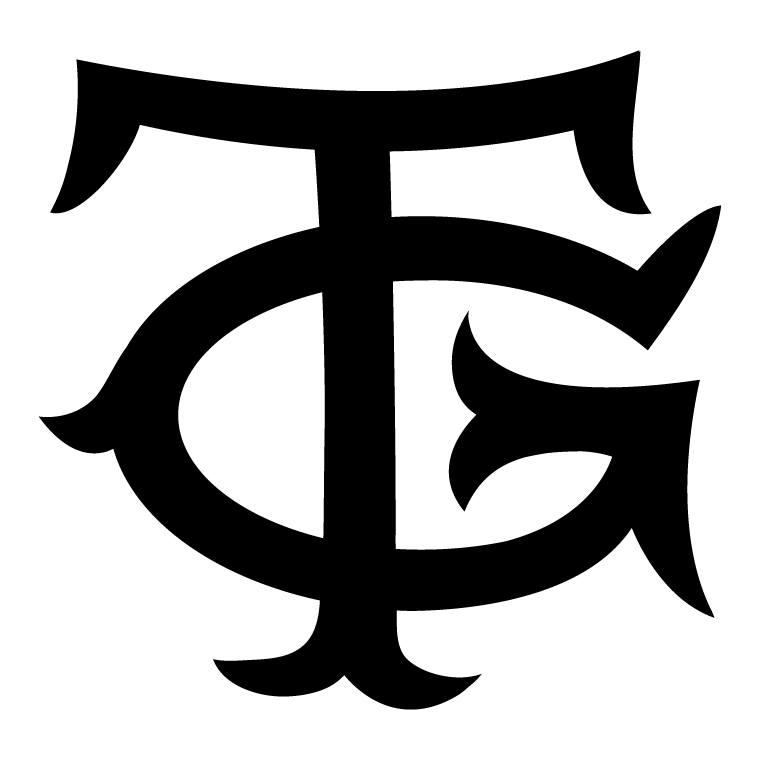
Name: Tommy Guerrero
DOB: 1966
POB: San Francisco, California, United States
Occupation: Skateboarder / Musician
http://www.tommyguerrero.com
https://www.instagram.com/tommyguerrero/
RECOMMENDS
-
MORE
耳に突き刺さる音。久保田麻琴(2/2)
常にホンモノの音を追求してきた氏が考える「耳に突き刺さる音」は、創る側の真剣さと優しさの土台の上にあって、そもそも人の持つ根源的なスピリットに触れるというゴールが聴く方にも無意識の中にある。だからこそ心が鷲掴みにされる。 […]
-
MORE
人が生きた痕跡のある音。久保田麻琴(1/2)
人が生きている痕跡のある音。ライフスタイルの上に在って、エッジのある強い響き。そういったスピリットを拾い続ける久保田麻琴。氏の中にある国境を越えて残るリアルな音について語る。 ぶっとい音 私が今やってることは、英語圏にあ […]
-
MORE
久保田麻琴と夕焼け楽団 × mocgraph ロゴTシャツ
久保田麻琴が「mocgraph(モックグラフ)」に登場!「人が生きた痕跡のある音」「耳に突き刺さる音」全二回のインタビューが公開されます。公開に合わせ久保田麻琴と夕焼け楽団の1stアルバム『SUNSET GANG』から石 […]


